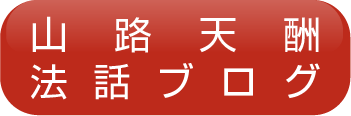品格について
令和2年2月7日
かつて藤原正彦氏の『国家の品格』、坂東眞理子氏の『女性の品格』を始めとして、〈品格〉という言葉が流行しました。
品格とは何でありましょうか。もちろん、今日・明日から品格を身に着けようとしたところで、叶うことではありません。その人の教養・思考・経験・生活・行動など、そのすべてが融合して自然ににじみ出るのが品格でありましょう。
たとえば、そこに紙くずが落ちていたとして、それを気にもしないか、気にはするけれども何もしないか、すぐに拾ってくず籠に入れるか、そんなところにも現れましょう。仏教では「下座の精進」といいまして、自分の立場や身分をいかに下げられるかを大事な修行としています。仏門に入る得度式は、礼拝の連続です。仏に向かって両膝・両肘・額を床に着ける〈五体投地〉をくり返します。つまり、高い品格は、自分を下げることから生じるという教えを実践するのです。下げることから心が清まり、魂が輝き、その品格が高まるのです。この逆説がわかりますでしょうか。
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」というではありませんか。稲は実るほどにその穂を下げるものです。人もまた、その品格が高いほど謙虚にふるまうものです。逆に品格の疑わしい人ほど尊大で、増上慢な態度をふるまうはずです。覚えはございませんか。
成長する会社の経営者は自らトイレ掃除をしたり、社員と同じ立場で対話をするはずです。社員もまたそんな社長を信頼し、仕事に励み、その会社が成長していきます。戦後日本を動かした偉大な経営者の方々を見れば、それは十分に理解できましょう。女性の品格も、国家の品格も、すべては謙虚でなければ高まりません。
墓前での甘酒接待
令和2年1月31日
私の郷里(栃木県芳賀郡の農村)にはめずらしい風習がありましたが、そのひとつをお話しましょう。
記憶はあいまいですが、あれは冬至の頃であったのか今頃であったのか、とにかく寒い時期に墓前での甘酒接待がありました。墓前といっても今のような霊園ではなく、昔の部落墓地でした。そこで大きな鉄なべで甘酒をつくり、道行く人に声をかけては甘酒をふるまっていました。道行く人も声をかけられると、ことわってはいけない礼儀があったような気がします。当時は自動車で通行する方など、ほとんどありません。徒歩や自転車の通行人が代わる代わる立ち寄り、その甘酒をいただいては去って行きました。
私はその甘酒が楽しみで、自分から進んで手伝いをしました。しかし、その意味を知ることもなく何十年も過ぎ去り、急に思い出したのもまた奇妙です。今は甘酒がブームらしく、スーパーにもたくさん並んでいます。それを見て連鎖反応があったのでしょう。
その由来を考えますと、どなたか、寺の住職でも提案したのかも知れません。要するに先祖に代って布施をなし、功徳を積むということなのです。何しろ寒い毎日で、温かい甘酒はありがたいものでした。昔はこんなことを通じて、仏教が民間に伝えられていたのです。しかも、何の不自然さもなく農村の風習になっていました。このようなお話はたくさんあるのですが、子供のころの記憶をたどると、なるほどと思うことがあって驚きます。民俗学という学問が生じるのも納得できます。
遠い日の記憶を思い出し、何やら楽しく、うれしい一日でした。さらに年齢を重ねれば、どんな記憶として甦るのでしょうか。
屈辱をバネに
令和2年1月30日
一昨日の塙保己一のお話には、さらに続きがあります。
ある雪の日、彼は平河天満宮(現・東京都千代田区)へ参詣しました。ところが参詣を終えての帰りぎわ、あいにくの雪のためか下駄の鼻緒が切れてしまいました。
境内に前川という版木商(今の出版業社)があり、人声を感じた保己一は「ヒモをいただけませんか」と頼みました。盲目の彼を見て、からかってやりたかったのでしょう。店の者が無言でヒモを放り投げたのです。彼は手さぐりでそのヒモを探しあて、鼻緒を仕立てようとしました。もちろん盲目の彼が、うまく仕立てられるはずがありません。店の者たちは手をたたいて笑いました。彼はその屈辱に耐えきれず、素足で店を飛び出しました。
ところが後年、幕府の推挙を得て『群書類聚』がいよいよ出版されるに及び、保己一は何とその前川を版元に選びました。何も知らない前川の主人がお礼を述べると、保己一は「私が今日あるは、数年前の雪の日に受けた屈辱のおかげです。むしろ私の方こそお礼を言いたいのです」と語りました。
天才とは、なるべくして天才になるのでしょう。屈辱の恨みを超えて相手を許し、むしろその屈辱を努力のバネにしたのです。誰しも、忘れがたい屈辱はあるものです。しかし、その恨みを報いるのに恨みをもってするなら、その恨みはいつになっても消えません。今度は相手が、さらなる恨みをいだくからです。保己一は仏典の教えを、深く体得していたのです。
『のどごし〈生〉』を生かす
令和2年1月29日
昨日、親しい不動産業の方が亡くなり、私が葬儀の導師を勤めました。八十三歳の天寿をまっとうしましたので、年齢に悔いはなかったと思いますが、人の一生には何かと未練や執着が残るものです。
私がちょっと驚いたのは、担当葬儀社の配慮でありました。いよいよ出棺の折、その葬儀社はあらかじめ葬主と話し合い、故人が生前に最も好きだった音楽CDを斎場に流しておりました。昨日、故人のそれはフジコ・ヘミングのピアノ演奏で、その美しい曲に一同が癒されておりました。これは現代葬儀においては、格別に異例なことではありません。このようなセレモニーは、他社においても流用していると思います。
私が驚いたのは、司会者の次の放送でした。「これから個人が生前に最も好きだったお酒を、ご遺族の方に綿棒でもってお口に含ませていただきます」と言うのです。故人はどんなお酒よりもキリンビールの『のどごし〈生〉』が好きだったらしく、ご遺族が代わる代わるその綿棒をお口に含ませました。こんな経験は初めてのことで、私は驚きつつも、何やら喜ばしい気持ちになったのも意外でありました。
しかし、どうでありましょうか。仏教の本義からいえば、葬儀とお酒は互いに相容れません。「不飲酒」は大切な訓戒であります。しかし、以前にもこの法話ブログに書きましたが、そこが神社や儒教、民間信仰と習合した独特の「日本教」なのです。神前にお酒や供物を献じてお祭りをなし、そのおさがりを仲よくいただくことが〝まつりごと〟なのです。つまり、飲食を共にすることで、人の気持ちが通じる〝政治〟となるのです。そして、その風習が仏教の中にも共存しているのです。
故人は生前に最も好きだった音楽を聴きつつ、最も好きだった『のどごし〈生〉』を奥様や子供たちからいただきました。もはや、この世の未練や執着から脱することは容易であったはずです。仏教の本義を離れて、立派な方便が生かされているようにも思えるのです。未練や執着を脱する方便として、『のどごし〈生〉』を生かしたのです。
五戒か十善戒か
令和2年1月22日
『あさか大師勤行式』の「回向勤行」には十善戒が記載され、法要のたびに皆様とお唱えしています。
十善戒とは不殺生(生きものを殺さず)・不偸盗(ものを盗まず)・不邪淫(性生活を乱さず)・不妄語(うそを言わず)・不綺語(たわごとを言わず)・不悪口(悪口を言わず)・不両舌(二枚舌を使わず)・不慳貪(貪りをせず)・不瞋恚(怒らず)・不邪見(間違った考えに走らず)のことです。始めの三つが行いの戒め、次の四つが言葉の戒め、最後の三つが心の戒めです。したがって、人は言葉に対する心がけがいかに大切であるかという教えでもありましょう。
これに対して五戒という教えもあり、不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒を指します。葬儀において戒名を読み上げる前に、このいずれかを授けるわけですが、どちらがよいのか私はかなり悩みました。
問題なのは五戒の不飲酒なのです。なぜかと申しますと、葬儀で五戒を唱えても、その後のお斎には「おきよめ」と称してビールやお酒が出されます。故人ばかりに不飲酒を戒めておきながらお斎をするのも、いかがでありましょう。またお斎の折には、故人の位牌や遺影の前にビールやお酒をお供えする方さえいます。これは日本の仏教が堕落したという意味ではなく、神前にお酒を供えて、そのお酒で仲よく直会(会食)を開く風習がこの国の宗教を支えて来たからです。つまり、仏教とはいっても、神社やいろいろな民間信仰が習合して、独特の「日本教」となったからです。仏式葬儀に不飲酒が生かされないのは、このような理由からなのです。
『あさか大師勤行式』に十善戒を選んだ理由はここにあります。お酒は人類の歴史と共にありますが、「百薬の長」ともいい、また「気ちがい水」や「百毒の長」ともいいます。願わくは「百薬の長」として、心身の健康に役立ってほしいものです。
お葬式はなぜ必要か
令和2年1月8日
新年早々、お葬式が入りました。私は初詣のため、日中は寺を空けられません。そこで昨夜の通夜のみお導師を勤め、本日はお手替の僧侶にお願いをしました。
現在、この国にはお葬式をしない方が急増しています。病院から霊柩車で火葬場に直行し、お骨のみ受け取る「直葬」という方式です。中には、お骨はいらないから〝処分〟して欲しいなどと申し出る人もいます。極端には新幹線の車内に、故意に置いていく人すらいます。
かつての日本人は、親の臨終にすら立ち会えないことを生涯の恥としました。また、たとえ借金をしてでも、親のお葬式ばかりはしました。どうしてこんなことになったのかといいますと、お金がかかるという理由からです。お葬式というと、高額なお布施がかかるし、葬儀社への費用も大変だということなのでしょう。
しかし、お金のことは、工夫をすれば低額で済ませる方法はいろいろあります。ネット派遣で僧侶を依頼すれば、お布施も安くなりますし、葬儀社の費用もさまざまです。事前によく調べてみることです。
そもそも、人生にはいくつかの節目があります。学校に入学するには入学式があり、卒業するには卒業式があります。また、成人すれば成人式があり、入社をするには入社式があります。それぞれの儀式があるから、それぞれの自覚が生まれるのです。そして、何より結婚をするには結婚式があります。今どきは教会式が多いことでしょう。神父さんが新郎新婦の手をとって、「お二人が夫婦であることを宣言します」と奏上するから、夫婦としての自覚が生まれるのです。
この世に別れを告げるにも、子や孫から何の挨拶もなく、お葬式らしい読経もなく、ただ火葬だけをされれる寂しさからは何の自覚も生まれません。そして、どこに往っていいのかもわかりません。
怖いお話をして恐縮ですが、お寺におりますといろいろ〝霊的〟な現象を体験します。真夜中で誰もいないのにインターホンが鳴ったり、読経中に玄間に人影を感じることがあります。中までは入って来ません。いや、入れないのです。そんな時私は、「お葬式をしてもらえなかった人だな」とスグにわかります。
皆様、何があっても親のお葬式ばかりはなさってください。あの世に旅立った親が、どこに往っていいのかわからないようなことにはなさらないでください。
スジャーターの乳粥
令和元年12月11日
お釈迦さまは悟りを開く前、六年間の苦行をしました。断食のため死の直前ともいえるほどに衰弱し、体は骨と皮ばかりになるほどでした。
その時、村の娘・スジャーターが通りがかり、持っていた乳粥の供養を受けました。そして、体力を回復したお釈迦さまはネーランジャラー川で身を清め、瞑想に入って、ついに悟りを開きました。これは仏教のことを少しでも学んだ方なら、どなたでも知っているお話です。ただ、問題なのはその「乳粥」とは何であるかです。
学者の中には「乳粥」を「ヨーグルト」と訳す方もおりますが、それは違っています。実はインドのお粥を「キール」と呼び、甘い味がするお祝いの料理なのです。甘いお粥というと、皆様は驚くでしょうか。しかし、お祝いに甘いものを出す習慣はよくあることで、日本でも東北や北海道の赤飯は甘く味付けします。また、甘い饅頭やぼた餅(おはぎ)などもその例でしょう。
ただ、その「キール」が、日本のインド料理店のメニューにはありません。私は僧侶の方にこのお話をする必要があった時、かなりの店に問い合わせました。しかし、東京銀座の「ナタラジ」という店でデザートとして出している以外、まったく皆無でした(だいぶ前のことで、最近はもう少し増えているかも知れません)。
「キール」は牛乳で煮つめたお粥に砂糖を加えます(さらにお好みでナッツ類を加えます)。牛乳を煮つめた状態を「蘇」といい、これも仏教では大切なものです。ついでですが、私は三十代にかなりの荒行をしましたのでわかるのですが、断食して極端に衰弱した時、ヨーグルトではさほどに体力はつきません。ところが、たとえ一杯でもお粥を食すれば、たちまちに回復します。
それだけに、スジャーターのお粥は甘く、また栄養価も高かったはずです。そして何より、彼女は一生を費やしても及ばぬほどの、大きな功徳を積んだのでした。
三歳の子供でも知っているが
令和元年12月3日
中国の唐代にはすぐれた詩人がたくさんいました。白居易(白楽天)もその一人です。実はその白居易には、仏教説話で語り継がれる有名なお話があります。
頭脳明晰な白居易が杭州の高級官僚となった頃、道林和尚という知られた禅僧がいました。いつも樹の上で座禅をしていたので、「鳥窠禅師」などとも呼ばれていたようです。「鳥窠」とは鳥の巣のことで、樹の上での座禅姿がまるで巣のように見えたのでしょう。
白居易はその道林和尚をからかってやろうと思い立ち、その樹下にやって来ました。白居易は樹の上で座禅する道林を見て、「危ないではないか」と言うや、すかさず道林は「危ないのはおまえさんだ。煩悩の炎が燃え上がっておる」と答えました。一本とられた白居易は、それなら、とばかりに「では、仏教とはどのようなものか」と問います。道林は「悪いことをせずに、善いことすることだ」と答えます。白居易はシメたとばかりに、「そんなことなら三歳の子供でも知っているではないか」と巻き返しました。道林は最後に、「三歳の子供が知っていても、八十を超えた老人でさえ行うことはむずかしいのだよ」とトドメを指しました。白居易はその場で、深く礼拝をして去ったのでした。
この道林の逸話は「衆善奉行(もろもろの善をなして)諸悪莫作(もろもろの悪をなさないこと)」の教えとして、大切にされてきました。まことに、「言うは易く、行うは難し」です。人は道理は知っていても、なかなか実行することができません。一つ善いことをしても、二つも三っも悪いことをするのが常なのです。
真理はやさしく、わかりやすいもののはずです。そして、平凡な言葉であるはずです。いいお話ですね。
台風の被害処理
令和元年10月21日
台風の被害処理が、まだまだ終わりません。
あさか大師も床下20センチが浸水し、御札や印刷物の一部が被害に遭いました。四分の一ほどが浸水しましたが、使えるものと使えなくなったものを仕分けしました。今はお護摩札を陰干しで乾燥させています(写真)。ニュースで放映される、あのような被害地に比べれば、まだまだ軽い方です。そして何よりも、お大師さまのご加護に感謝しています。

昨日は第三日曜日の行事で、お弟子さんやご信徒の方が集まり、いろいろとお手伝いいただきました。ありがたいことでした。この時期、祈祷寺院は早くも正月準備に入らねばなりません。やらねばならないことは多いのですが、被害処理をしながら多くのことを考えました。
私は平和な時代に生まれ、平和な時代の中で育ちましたので、これが初めて経験した災害です。埼玉県は津波も噴火も土砂崩れもなく、台風もさほどには通過しません。まず、災害の少ないところなのです。しかし、今回は異例としても、これからはわかりません。このクラスの台風がたびたび通過する可能性はありますし、これまで考えられなかった河川が氾濫する可能性もあります。それに、地震や火災への備えも怠れません。
いつも思うのですが、「平和で安心して暮らせる社会」など、あるはずがないのです。今回の台風で、その思いをいっそう確信しました。すべては〈無常〉なのです。永遠のものも、絶対のものもないのです。この世のすべては移り変わるからです。その覚悟をもって生きてこそ、イザという時に智恵が湧くのです。だから、〈諸行無常〉は前向きに生きるための智恵なのです。仏教が説く大切な真理です。
初恋の味
令和元年10月10日
日本初の乳酸菌飲料「カルピス」のお話です。
カルピスの創業者・三島海雲は、現在の大阪府箕面市、教学寺の長男として生まれました。文学や英語を学び、仏教の大学にも進みましたが、やがて中国で起業する志を立てました。ある日、北京から内モンゴルに入り、遊牧民が飲む乳酸がとても体によいことを知りました。
海雲はこれを日本で発売することはできないかと考え、さまざまな試行錯誤を重ねて、ついにカルピスを完成させました。彼はカルピスの本質を、おいしいこと、滋養になること、安心感があること、経済的であることとし、国家の利益となり、人々の幸福につながる〈国利民輻〉を事業の理念としました。
ところで、仏教では最上の練乳の味をサルビスといい、日本では〈醍醐〉と訳されています。カルピスの商標を決める時、カルシュウムとサルビスを合わせ、〈カルビス〉〈カルピス〉〈カルピル〉の三つの候補が上がりました。これを『赤とんぼ』の作曲者・山田耕作に相談したところ、「カルピスが最も語呂がよい。大いに繁昌するでしょう」と太鼓判を押されました。これが商標「カルピス」の誕生秘話です。
また、海雲の文学仲間であった驪城卓爾にカルピスを飲ませたところ、「甘くて酸っぱい。カルピスは初恋の味だ」と答えました。海雲が「カルピスは子供も飲む。子供に初恋の味って何だと聞かれたらどうする」と迫ったところ、驪城は平然と「カルピスの味だと答えればいい。初恋は清純で美しいものだ。また初恋という言葉には、夢と希望と憧れがある」と語り、海雲はもはや何も言えませんでした。これがキャッチフレーズ「初恋の味」の誕生秘話です。
一途に甘く、微妙に酸っぱいカルピスは、仏教語を含んだ初恋の味なのです。カルピスを飲めば、あのときめき(!)を思い出せるのです。