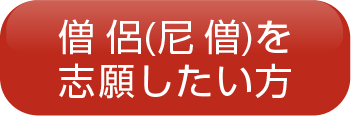半鐘はなぜ打つのか
令和6年10月24日
あさか大師の本堂内に、半鐘が設置されました(写真)。

半鐘はお護摩やご回向開始の合図として打ちます。この大きな響きを聞くと、僧侶も参詣の皆様も姿勢を正し、気持ちを引き締めるものです。
半鐘の打ち方には「一通三下・三通三下
・終鐘」などがあります。〈一通〉とは大きく7打して後、しだいに早くしつつ35打します。〈三通〉はこれを3回繰り返します。〈三下〉とは一通、または三通した後、大きく3打して終わるという意味です。
つまり、三通三下は合計108打することになり、一〇八煩悩の眠りを覚ます意味であることは申すまでもありません。このほかにも法要の最後に打つ終鐘がありますが、今は省きます。
半鐘の音は「警鐘」でもありましょう。自らを戒める警告なのだと、私は思っています。いかが。
魂をゆさぶる一周忌法要
令和5年7月23日
私が40年間も交友を重ねた八丈太鼓(八丈島の郷土芸能)の伝承者・只道和尚が昨年7月に他界し、昨日はその一周忌法要をいたしました。只道和尚は若くして曹洞宗の僧侶となりましたが、志すところあって在俗生活をなしつつ、八丈太鼓の修練と弟子の養成に人生を捧げました。
他界する少し前、私は和尚から三つの依頼を受けました。一つには自分の葬儀導師を引き受けてほしいこと。二つには自分の遺骨をあさか大師に納骨してほしいこと。三つには自分の本尊・不動明王像をあさか大師に安置してほしいことでした。すでに一と三の依頼は果たしましたが、二に関しては、もうしばらくの時間がほしいと生前にお話をしました。
さて、今日の一周忌法要はまず私がお導師を勤め、一般の法事と同様に挙行しました。ところが、せっかくの一周忌法要であるから「偲ぶ会」として、霊前に弟子の八丈太鼓を披露しようということになりました。そこで直弟子はもちろんのこと、和尚が指導した和太鼓奏者や舞踊家、シンガーの方々などが集まり、にぎやかで楽しい「偲ぶ会」となりました。また、和尚は障害者施設でも和太鼓の効能を提唱して指導したため、たくさんの皆様がマイクロバスで参集くださいました(写真)。

和太鼓ほど魂をゆさぶり、心の抑圧を開放する楽器はありません。八丈太鼓はたった一台で下拍子に合わせて上拍子をアドリブで奏します。また独特の島唄が加わり、迫力と共に深い郷愁に誘われます。あさか大師では法楽太鼓や法螺貝の音色が遍満しますが、今日ばかりは堂内に八丈太鼓が響き渡り、異色の一周忌法要に一同が随喜しました。このような時、人は自他の区分を離れ、感動の中で心を融合させるものです。長年にわたって葬儀や法事に関わりましたが、このような事例はありませんでした。とんでもない友人を持ったものです。もう一つの約束を果たさねば、私もあの世で顔向けが立ちません。
それにしても、和太鼓が世界中で人気を集めるのも、大いに納得しました。子供たちにも、高齢者にも、自信をもって奨励したいと思います。
今年最初の総回向
令和2年1月11日
今日(土曜日)と明日(日曜日)は、今年最初の総回向(光明真言土砂加持法要)を修す日です。午前中は厄よけのお護摩や平日のお護摩をなし、午後一時から総回向を修しました。普通なら今日の土曜日の方が多く集まるのですが、ちょっと寂しいほどでした。それでも新しく天台宗僧侶の方がお見えになり、いっしょに読経をしてくださいました。
また法要の後、令和二年庚子・七赤金星はどんな年になるか、九星盤を使って説明しました。一昨日、ブログにも書きましたが、皆様が興味をもって聞いてくださいました(写真)。

今年は何といっても2020東京オリンピック・パラリンピックの開催により、多くの外国人がさらに集まり、国内が遊興的ムードになることは間違いありません。まさに七赤金星を象徴するかのようです。ただ、相変わらず災害への懸念も否定できません。少しでも災害対策のノウハウを学び、普段から備えを心がけましょう。
また、今年の春彼岸中日は三月二十日です。一日違いですが、この日にお大師さまの正御影供(お御影を供養する法要)を修したいと考えております。一年間祈念しました光明真言の〈お土砂〉も授与いたします。いろいろな使い方ができるので、これもまた、少しずつ説明いたしましょう。明日もまた、総回向の法要をいたします。
あの世はここにあります
令和元年8月4日
炎天下の中、今日も月初めの総回向・光明真言法要にお集りいただきました。
法要の最後に、〈光明真言和讃〉という、その功徳を称えた歌詞を唱えるのですが、皆様が大変に慣れ、またお上手になりました(写真)。

この法要には、僧侶の方も会員になっていらっしゃいます。私は僧侶の方にこそ、 この光明真言の行法を修していただきたいと、日頃から切に願っています。なぜなら、僧侶の方(特にご住職)は檀家の葬儀・法事には熱心ですが、ご自分の家や奥様ご実家の先祖に対して、あまりにも無頓着であるからです。
もちろん、お寺にも家の仏壇があるでしょうし、先代の回忌法要などはなさるでしょう。また、たいていは奥様が、毎日のお水やお茶のお供えぐらいはなさっています。しかし、それ以上のことには熱心ではありません。
そもそも、人はこの世とあの世を共に生きているという発想がありません。私たちは眼には見えず、耳には聞こえずとも、あの世と共に生きており、あの世そのものが〝ここ〟にあるという視点を持っていただきたいのです。回忌だから法要をするのではなく、いのちの根本に対する日頃からの配慮が必要なのです。
私たちは男性なら母方に、女性なら父方に、必ず似たような性格、似たような体質の方がおります。これは死亡によって終ったのではなく、いのちを継続をしているという事実にほかなりません。
私の寺へお越しになった僧侶の方にこのことをお話し、図(ホームページ先祖供養を参照)でも説明しますと皆様が納得され、熱心な会員になってくださいます。
私自身も最近『光明真言法』を出版し、その普及に励んでいますが、この件はまた明日にでもお話しましょう。夜になっても、なかなか涼しくなりません。水分・塩分・クエン酸の補給、お忘れなく。
盂蘭盆法要
令和元年7月6日
あさか大師では本日と明日、早くも盂蘭盆法要となります。
本日は僧侶の方々も集まり、お施餓鬼を全員で修しました(写真)。お導師(私)の右側に施餓鬼壇があり、お粥や野菜や水を献じました。ご信徒の皆様も読経や真言がお上手なので、心強いかぎりです。また、遠くから何十年ぶりに越しくださった方もあり、うれしい一日でした。

夏になると、お寺ではお施餓鬼をしますが、もともとは盂蘭盆法要とお施餓鬼に直接の関係はありません。盂蘭盆法要は供物を献じ、読経や布施をして、その功徳をご先祖に回向することが目的です。その供物を献じた器が〝お盆〟なのです。このお話、覚えておいてください。
お施餓鬼は餓鬼界に堕ちてしまった人を救うことが目的で、野外で修するのが本来の作法です。でも、双方とも夏の風物によく合うことは間違いありません。
ちょっと怖いお話ですが、餓鬼界に堕ちた人は、喉が渇いてはりついているため、飲むことも食べることもできません。そこで喉を開き、飲めるように食べるようになし、さらに甘味や水分を加えるのがお施餓鬼の作法です。だから、お施餓鬼を熱心に修した僧侶は、喉や胃を病むことことがなく、長命であるとされるのです。このことは、私が師僧から聞かされたお話です。肝に銘じねばなりません。うれしい一日でもあり、戒めの一日でもありました。
あの世とこの世
令和元年5月4日
今日は月初めの行事日で、午前11時半よりご祈祷のお護摩を、午後1時よりご回向の光明真言法要がありました。皆様、熱心に参拝し、自ら読経もなさっておられました。写真は午後の法要のものです。
回忌法要
平成31年4月28日
今日は朝から十三回忌法がありました。母上様のお位牌とお写真をご持参されました(写真)。法要の後はご家族とご兄弟が墓前で合流なさるそうでございます。
水子供養の霊験
平成31年4月2日
あさか大師での〈水子供養第一号〉の方のお話でございます。
昨年の12月に、私はこの寺に越してまいりました。ほとんど身辺の片づけもできぬまま正月準備に突入し、さらに毎日の法務にも明け暮れておりました。そんなある日、ご自分のお嬢様が結婚して3年以上もたつのに、まだ子宝に恵まれないというご相談を受けました。
そこで私は、そのお母様には水子さんがいないかと尋ねたのでございます。するとそのお母様は、その子と一緒に生れはしたけれども、すぐになくなった子がいることをお話しされました。私はさっそく、「戒名をつけて永代供養をしてあげましょう」とおすすめしました。そのお母様は承諾し、これがあさか大師での水子供養第一号(生まれていますので、正確には嬰子となりますが)となりました。その子のお位牌はいま水子観音堂に安置され、毎日のご供養を受けております。
正御影供と春彼岸法要
平成31年3月21日
春彼岸中日。しかも弘法大師(お大師さま)ご入定の日なので、真言宗の寺では正御影供(お大師さまのお姿に供養をする法要)を修します。毎月21日のご縁日の法要は単に「御影供」といい、この日ばかりは「正御影供」と申します。もっとも、お大師さまご入定の承和2年(835年)3月21日は旧暦でのお話なので、これを旧暦に換算して法要をしている寺もございます。
私は毎年午前中に正御影供を、午後には春彼岸法要を修しております。今日は畏友の豊島泰國師(宗教作家・占術家)がわざわざお越しくださり、久しぶりに旧交を温めました。