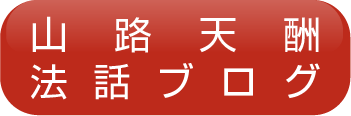令和2年1月22日
『あさか大師勤行式』の「回向勤行」には十善戒が記載され、法要のたびに皆様とお唱えしています。
十善戒とは不殺生(生きものを殺さず)・不偸盗(ものを盗まず)・不邪淫(性生活を乱さず)・不妄語(うそを言わず)・不綺語(たわごとを言わず)・不悪口(悪口を言わず)・不両舌(二枚舌を使わず)・不慳貪(貪りをせず)・不瞋恚(怒らず)・不邪見(間違った考えに走らず)のことです。始めの三つが行いの戒め、次の四つが言葉の戒め、最後の三つが心の戒めです。したがって、人は言葉に対する心がけがいかに大切であるかという教えでもありましょう。
これに対して五戒という教えもあり、不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒を指します。葬儀において戒名を読み上げる前に、このいずれかを授けるわけですが、どちらがよいのか私はかなり悩みました。
問題なのは五戒の不飲酒なのです。なぜかと申しますと、葬儀で五戒を唱えても、その後のお斎には「おきよめ」と称してビールやお酒が出されます。故人ばかりに不飲酒を戒めておきながらお斎をするのも、いかがでありましょう。またお斎の折には、故人の位牌や遺影の前にビールやお酒をお供えする方さえいます。これは日本の仏教が堕落したという意味ではなく、神前にお酒を供えて、そのお酒で仲よく直会(会食)を開く風習がこの国の宗教を支えて来たからです。つまり、仏教とはいっても、神社やいろいろな民間信仰が習合して、独特の「日本教」となったからです。仏式葬儀に不飲酒が生かされないのは、このような理由からなのです。
『あさか大師勤行式』に十善戒を選んだ理由はここにあります。お酒は人類の歴史と共にありますが、「百薬の長」ともいい、また「気ちがい水」や「百毒の長」ともいいます。願わくは「百薬の長」として、心身の健康に役立ってほしいものです。