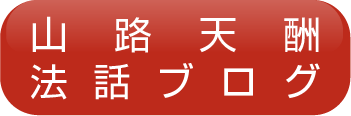令和2年5月21日
昭和の時代に岡潔という天才数学者がいました。『春宵十話』という随筆集も残していますが、天才にありがちが奇行も多く、「希代の仙人」とか「現代のアルキメデス」などとまで呼ばれていました。
京大理学部卒業の後、フランスに留学して理学博士となりましたが、「私の研究に必要なものは俳句である」と言って松尾芭蕉の研究に没頭する始末でした。数学には美意識こそ大切だという考えがあったからです。そして二十年後、世界中の数学者が誰も解けなかった〈三大難問〉を独力で解き明かすという快挙を成し遂げました。「もしノーベル数学賞があれば、間違いなく受賞したであろう」とまで言われています。
家族五人の生活は極貧で、財産もすべて売り払い、一時は物置小屋を借りてやっと飢えをしのぐほどでした。いつもよれよれの背広にノーネクタイ、長靴だけをはいて歩いていました。「ネクタイは交感神経をしめつけ、革靴は歩くと頭に響くので思考を妨げる」と言い張っています。文明の利器とは縁がなく、奥さんが電話を引いてくれるよう頼んでも、「あれは俗物の代物だ」と言って聞き入れませんでした。それでも奈良女子大教授となってからは、生活もいくらかは楽になりました。そして、数学の研究を始める前の一時間は、いつもお経を唱えていました。
昭和三十五年には文化勲章に輝きましたが、この時ばかりは家族の説得でやっと革靴をはいたという〝伝説〟があります。その受章祝賀の席で天皇陛下より「数学とはどういう学問ですか」と問われると、「数学は生命の燃焼です」と答えました。また新聞記者から「数学で最も大切なものは何ですか」と問われると、「野に咲く一輪のスミレを美しいと思う心です」と答えました。
数学の研究と美意識がどう結びつくのか、私たちにはわかりにくいかも知れません。しかし論理的に数学を考え、また考えて、その最後にひらめく感覚は、美しいものを見て感動する心に通じるのではないでしょうか。だから、数学は生命の燃焼なのでしょう。私は野の花を(普通の花瓶ではなく)よく古い仏具や土器に挿しますが、花を習ったことは一度もありません。それでも、一輪の花が何を語っているのか、どんな器に入れて欲しいのかはよくわかります。そのことはお大師さまの教えを学ぶうえで、大変に役立ちました。
美しいものを見て感動する心がなければ、最後のひらめきには到達しません。自然を見て感動し、絵画を見たり音楽を聴いて感動する時、偉大な科学的発見が生まれるのはこのためです。仏師が木材の中に仏を見い出して仏像を彫るように、数学の埋もれた真理も感動する心から掘り出されるのだろうと思います。昭和の偉大な天才数学者は、まさに「数学の詩人」であったのです。