スーパー・ウルフムーン
令和8年1月4日
昨夜は東の空から「スーパー・ウルフムーン」が昇りました。4回連続スーパームーンの最後を飾るにふさわしい、みごとな満月だったと思います(写真)。
 新春3日目の初詣を終えて一息ついた時、思わず隣の土手にはい上がりました。毎日、日の出を拝んで意気を高揚させていますが、今度は満月によって疲れが癒されました。
新春3日目の初詣を終えて一息ついた時、思わず隣の土手にはい上がりました。毎日、日の出を拝んで意気を高揚させていますが、今度は満月によって疲れが癒されました。
生きていることの喜びとは求めるものではなく、このように与えられるものなのでしょう。餅をつくウサギさんを抱きよせたくなりました。
そういえば「抱月」という雅号を、とても気に入っていた遠い記憶があります。今日も頑張らんないと。
10月に桜が咲いた
令和7年10月21日
「秋桜」とはコスモスのこと。ほかに「十月桜」という品種があり、春と秋とに二度咲きます。ところが、ソメイヨシノでありながら、10月に開花する奇妙な現象があります。あさか大師の桜並木にも、わずかながら花開いた姿が散見されました(写真)。

まず、この夏の猛暑が関係していることは、容易に推測されましょう。すでに落葉しているのに、何らかの影響で植物ホルモンの働きが変わったように思われます。桜もこの異常気候には迷うばかりです。
野菜や果物の栽培、魚の水揚げも変わりました。スーパーから日本の果物が消え、熱帯地の魚ばかり並ぶ時代が来るのでしょうか。かつて「終末」という言葉が流行りましたが、その終末を乗り越えるべく、私たち一人一人ができることをしなければなりません。この地球も、この日本も、私たちが住む大切な自然です。
今宵は新月。蒼茫とした木立に光はなく、水墨画のような景観が闇に迫ります。地球はいずこに、日本はいずこに。
この世の月、あの世の月
令和7年10月7日
幼い頃、東の空に昇った月の隣りに、もう一つの淡い月の姿を見たことがありました。私は何だろうと思いつつも、誰に話すこともなく、記憶からもしだいに薄らいでいきました。
ところが三十代になって、ある山奥の断食道場に入門した折、二つの月を描いた絵が目につきました。その意味を道場主に問いましたところ、「片方はあの世(霊界)の月です。あの世にも、この世と同じように月があるのです」という答えでした。私はたちまち幼い頃の記憶が甦り、あ然としたものでした。後年、私が「双月子」という雅号を名のったのは、この体験からの由来です。
昨夜は陰暦八月十五日の〈中秋名月〉でした。そして今夜が天文上の満月で、一日のズレがあります。関東地方はいずれも曇り空で、残念ながら〈お月見〉が叶いません。
そこで、あの世の月に供える意味で、ススキとお団子(弟子僧の手作り)を飾りました(写真)。ススキの右上あたりに、あの世の月があるかも知れません。花器は平安時代の瓦製経筒で、写経を埋葬した容器です。

見えない月に供えるのも粋なものです。境内の地面と、桜並木と、曇り空がおりなす影絵に、お供えが映えました。桜木の枝は重なり、暗夜の虚空に秋のレジェンドがそこにいます。
彼岸花の妖艶
令和7年9月25日
あさか大師桜並木の下に〈彼岸花〉が群生し、その妖艶な姿がお参りの皆様を楽しませています(写真)。

「曼珠沙華」という別名もありますが、これは仏典に由来するサンスクリット語で「天上の赤い花」という意味です。かつては「死人花」「地獄花」などとまで呼ばれ、お墓の花と見なされていました。また茶花や生け花でも〝禁花〟とされ、これを用いることはありませんでした。
ところが今や群生地は人気の的で、たくさんの人々が集まります。特に本県・日高市の〈巾着田〉は〈曼珠沙華まつり〉が催され、約30万人が訪れます。たしかに、秋の野山に咲きほこる真っ赤な花は美しく、元気を与えられ、お彼岸にもふさわしい姿です。
まだまだ残暑が続いていますが、朝晩は涼やかな風が吹き、秋らしくなってまいりました。今日は真っ青な空に、赤い花がよく似合います。
突き抜けて 天上の紺 曼珠沙華(山口誓子)
偉大なる植物のドラマ
令和7年6月29日
10年ほど前、塚谷裕一著の『スキマの植物図鑑』(中公新書)という本が話題になりました(写真)。
同書は街角のコンクリートやアスファルトの割れ目、石垣や電柱の根元といったわずかなスキマから、植物たちがいかにたくましく成長しているかを紹介した異色の刊行でした。しかも、植物たちがいかにも窮屈で息苦しく生きているのではなく、何とも居心地よく幸福に過ごしている様相を発見することに、同書の主張がありました。
人間はあくせくと働き、動物は餌を求めてさ迷っているというのに、こうした植物は一ヶ所に根を下ろしたまま、光と水と肥料を十分に吸い、実に豊穣な時間を過ごしているのです。都会の片隅、国道わきの騒がしい環境にあっても、それは同じです。何と偉大なるドラマでありましょうか。
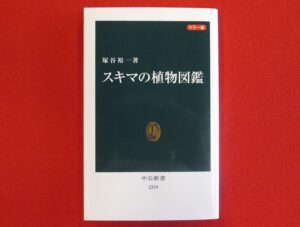
こうした植物の様相は、通勤中の通り道、買い物や散歩の道端、公園や工事現場、いたるところに見い出せましょう。その飄々たる楽園を讃嘆するならば、私たちは何も見えていなかった自分に驚くのではないでしょうか。自分の足元に、かくも偉大なドラマがあるというのに、いったい何を見て生きていたのでありましょうか。
あさか大師の境内でも、ドラマは常に見い出せます(写真はエノコログサ)。ああ、植物は偉大なり。偉大なるドラマに幸あれ。

「仏の座」が開く
令和7年2月23日
あさか大師の周辺には〈仏の座〉が花開いています。田畑を埋め尽くし、まるで赤紫のジュウタンです(写真)。

よく混同されますが、「春の七草」のホトケノザとはキク科の〈コオニタビラコ〉のことです。この〈仏の座〉はシソ科で、残念ながら食用にはなりません。
ところが、葉が茎に抱きつき、その上に花が乗る様相は、まさに仏様の台座に似て、「ホトケノザ」と呼ばれるようになりました。散歩の途中でも目にするでしょうから、ぜひ観察してください。先端の小花が仏様にも見えましょう。
春はすぐそこ。霜を浴びても枯れず、倒れず、陽光に彩り、浄土のように華やぎます。うららうらら。
「幸せホルモン」を増やす方法
令和6年1月28日
「幸せホルモン」のセロトニンを増やすには、太陽の光を浴びるのが一番です。特に日の出の輝きには、脳内環境を一変させる何かがあります。あさか大師での冬は正面より日の出がありますので、私は毎朝これを拝し、真言密教の特殊な日輪観を修しています(写真)。この後にお大師さまへのお勤めに入りますが、幸せでさわやかな気持ちになることは間違いありません。

セロトニンは闘争ホルモンのアドレナリン、恐怖ホルモンのノルアドレナリン、睡眠ホルモンのメラトニンなどを制御して、幸せな気持ちに導いてくれます。しかも太陽の光だけで増えるのですから、費用もかかりません。
このほか、ウォーキング・ストレッチ・スクワットなどの運動によって、またサプリメントまでも販売されていますが、太陽の光を浴びるのが最も簡単で誰にでもできる方法です。時間についてはいくつかの説がありますが、私は3分~5分ほどでよいと思っています。ぜひ試してみてください。
幸せな朝は、その一日を豊かにしてくれます。大日如来と日天の神さまから、幸せのパワーをいただきましょう。
名月の癒し
令和5年9月29日
月面の温度は昼が110度、夜は-170度で、その寒暖差は280度です。生物が生息できる環境ではありません。
それでも私たち日本人は、うさぎがお餅をつき、かぐや姫の故郷であることを口にしても、何の違和感もありません。忙しい現代人でも、それは同じです。仕事に疲れた夕暮れ時に、また夜の静寂にふと月を見る時、私たちはどれほど癒されることでしょうか。ホッとするひと時とは、まさにその瞬間なのです。
今宵は旧暦8月15日で、中秋名月です。あいにく雲が多く、残念ではありますが、ほんの一瞬その美しい姿を見せてくれました(写真)。

昨夜が〈待宵〉、明日が〈十六夜〉、そして来月27日(旧暦9月13日)が〈十三夜〉です。何と美しい日本語でしょうか。月まで行ける時代だからこそ、昔のように月を想い、月を偲びましょう。その時、あなた様の人生がとても豊かで幸せなものになりますよ。
まさに地球沸騰化!
令和5年9月27日
ヨーロッパ連合の気象情報機関によれば、今年7月の平均気温は観測史上最も高くなったと発表し、12万年ぶりの暑さとの報道もありました。また国連のグテーレス事務総長は、「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」と発表しました。
海水の温度が上がってエルニーニョ現象が発生し、世界のいたるところで台風・豪雨・ハリケーンなどの異常気象を引き起こしています。世界中の人々が、この異常気象に危機感をいだいていることは申すまでもありません。地球はもはや、未曽有の異変に直面していることは誰の目にも明らかです。
私が特に危機感をいだいたことは、秋のお彼岸に至っても、境内となりのヒガンバナがわずかな開花であったことでした。前回のブログで秋彼岸法要のことを書きましたが、例年なら真っ赤に埋め尽くされるはずなのです。お彼岸の明けた今日はやっと咲き出しましたが、それでも例年に比べればまだまだ足りません(写真)。各地の群生地でも同じだと思います。まさに地球沸騰化の証明でありましょう。

このような現象は、人間側に原因があるはずです。いま必要なことは、私たち一人一人が謙虚に反省し、何ができるかを考え、行動に移していく以外にはありません。大気中の温室効果ガスを少しでも減らす努力を決意しましょう。そして、秋のお彼岸に日本の野山が、再びヒガンバナに彩られる日を実現したいものです。春のお彼岸にはモクレンが、お盆にはハスが、そして秋のお彼岸にはヒガンバナが咲く、日本は仏の国なのだと、私はいつも思っています。
続・花は自然界の名医です
令和5年3月18日
私はお風呂くらいは、時間をかけてゆっくりしようと考えましたが、どうしても長湯にはなれませんでした。ある時、作家の五木寛之さんが、お風呂の中で本を読んでいるというエピソードを聞き、私も真似をしてみようと考えました。仕事には関係のない小説でも読んでいれば、少しは長湯になるだろうと思ったからです。
五木さんは時には眠りに誘われたりして、湯の中に本を落とすこともあるそうで、ぶよぶよになった本が書棚に並んでいるそうです。私も危うい経験をしましたが、何とか事なきを得ました。たしかにお風呂に本を持ち込めば、時を忘れて読みふけることもあり、かなりの成果があります。ぬるめのお風呂に長くつかって体温を上げたい方には、お勧めの方法です。ただし、愛書趣味の方には向きません。湯の中に落とさずとも、湯気で変形することは避けられないからです。
ところが昨年の暮、正月飾りのセンリョウ(千両)が余ったため、コップに挿してお風呂の片隅に置きました。すると、これが癒しの空間になったのです。今度は本を持たずとも、いつの間にか長湯になりました。ユニットバスの中に別世界が出現したようで、思わぬリラックスタイムを得たのです。今日はフリージアが置かれています(写真)。

私は湯の中に入ったら、まず呼吸法をなし、目を細めて花が何を語るかを感じ取ります。そして、花の〈気〉が自分の頭上(百会というツボ)より入って全身を巡ると観じます。次に自分が花に返す想いを口元から発し、花の精を巡ると観じます。自分と花との一体感が生まれ、極上のひとときとなる喜びはたとえようもありません。一日の疲れを癒し、心身の不調すら癒されるからです。宝物とは、これほど身近にあるのでしょうか。
女性はよく花を買い求めますが、男性で見かけることはほとんどありません。しかし私は、男性こそ花を買い求め、自分への癒しにしていただきたいと考えています。私は道端や土手の、野の花にこそ癒されるほどです。少しずつ形や色を、そして名前を覚えれば、これもまた宝物です。そして、花は自然界の名医であることを知るでしょう。


